【セッションレポート】クラウドストレージのコスト最適化戦略 – AWS ストレージの賢い活用法 #AWS Summit Japan 2025
はじめに
こんにちは、Paseri です。
この記事は、AWS Summit Japan 2025 のセッションである「クラウドストレージのコスト最適化戦略 – AWS ストレージの賢い活用法」のレポート記事です。
Amazon S3 と、Amazon EBS に焦点を当ててコスト最適化のアプローチ手法を紹介しているセッションですので、興味のある方は是非ご覧ください。
ちなみに、本セッションは AWS Summit Japan サイトからユーザー登録いただくことでアーカイブ視聴が可能なセッションとなっておりますので、気になった方はぜひ見てみてください!
AWS Summit Japan 2025
ユーザー登録はこちらから
※本情報は、2025年6月30日時点での情報となります。
セッション情報
タイトル
クラウドストレージのコスト最適化戦略 – AWS ストレージの賢い活用法
スピーカー
榊原 直道 様
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 技術支援本部 エンタープライズサポート テクニカルアカウントマネージャー
概要
AWS ストレージは、データ保存の柔軟性と拡張性を提供しますが、適切な設計とモニタリングがなされない場合、意図したコスト構造とならない可能性があります。本セッションでは、AWS のオブジェクトストレージ (Amazon S3) とブロックストレージ (Amazon EBS) に焦点を当て、サービスの紹介と料金モデルから始まり、コスト最適化の実践的なアプローチ、機能、モニタリング方法を紹介します。このセッションを通じて、クラウドストレージのコストの実践的な知見を得ることができ、利用者自身でコスト最適化が実施できるようにしていただけることを目標とします。
セッションレポート
このセッションでは、S3 と、EBS に対してどのようにコスト最適化のアプローチを実施するのかについて説明していました。
データに関する将来的な不安がある方や、ストレージに対するコスト最適化の手法を学びたい方には参考になるセッションです。
1. Amazon S3 コスト最適化アプローチ
このセクションでは、2 つのユースケースに対するアプローチを紹介していました。
ケース 1:アクセスパターンが既知または予測できるデータ
この場合、活用できる機能として「ライフサイクルルール」が挙げられていました。
アクセスパターンが予測できるため、オブジェクトの経過時間に基づいて S3 Standard から S3 Standard-IA や、S3 Glacier の各クラスへ自動移行、または期限切れとしてオブジェクト自体を削除することでコスト削減を実施します。
また、さらに詳細なライフサイクル設定を行うことで、オブジェクトの移行にかかるコストも最適化し、サイズの小さいオブジェクトはあえて移行しないという設定が可能です。
単に全てのデータをアーカイブにすればいいというわけでもないんですね!
ケース 2:アクセスパターンが不明または変化しているデータ
このユースケースは多くの方が直面するのではないでしょうか。
この場合に活用できる機能として、「S3 Intelligent-Tiering」というサービスがあります。
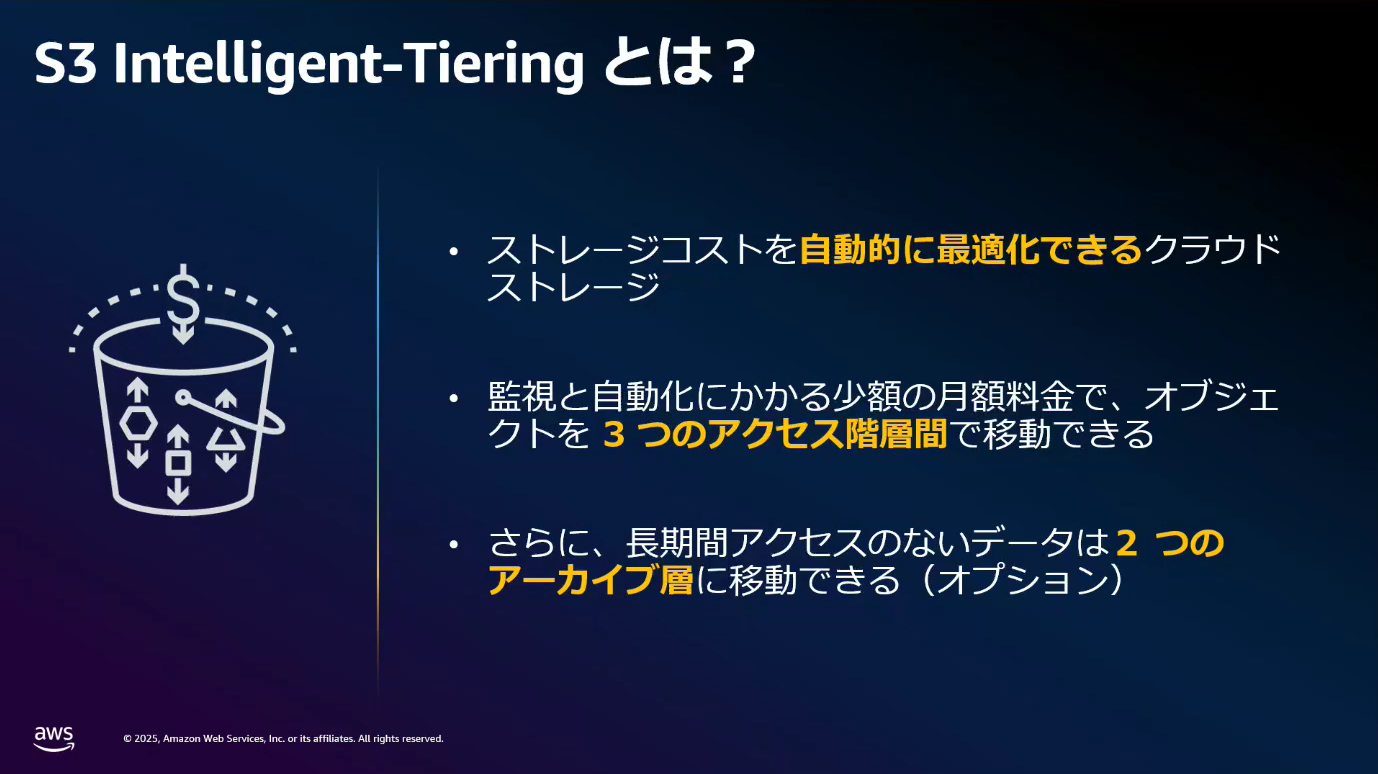
出典:クラウドストレージのコスト最適化戦略 – AWS ストレージの賢い活用法
S3 Intelligent-Tiering は、オブジェクトに対する経過時間ではなく、「アクセス頻度」を分析して自動的に最適化してくれる機能です。
アクセス頻度に応じて、3 つのアクセス階層間でオブジェクトを移動してくれます。
- 高頻度アクセス階層
- 低頻度アクセス階層
- アーカイブインスタントアクセス階層
例えば、特定のオブジェクトに対して 30 日間アクセスが無かった場合、それを検知して低頻度アクセス階層へ自動的にデータを移行してくれます。また、その後 60 日間アクセスが無い場合、今度はアーカイブインスタントアクセス階層へ移行することで最大 80% のコスト節約が可能になります。
この機能を活用することで、ライフサイクルルールの経過時間で考慮することなく、S3 のコスト最適化を行うことができる、というわけです。
可視化ツールの利用
また、オブジェクトのアクセス分析を実施できるツールとして 2 つほど紹介されていました。
- Amazon S3 Storage Lens
- S3 のダッシュボードから確認でき、組織全体のストレージ状況を可視化することができます。
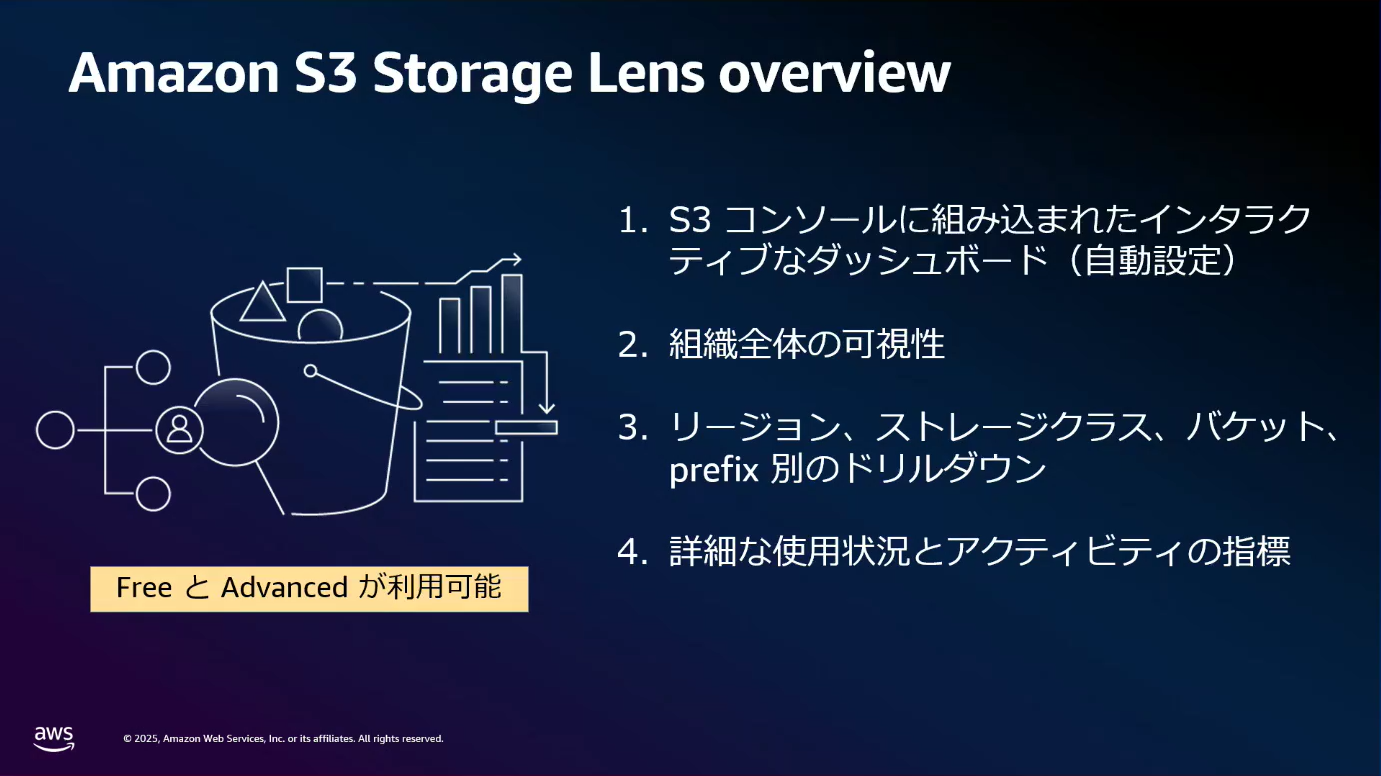
出典:クラウドストレージのコスト最適化戦略 – AWS ストレージの賢い活用法
- ストレージコスト分析
- オブジェクトに対するアクセス頻度と経過時間を分析し、移行推奨日をレコメンドしてくれます。
2. Amazon EBS コスト最適化アプローチ
このセクションでは、EBS のボリュームタイプの最適化と不要リソースの管理について説明されていました。
ボリュームタイプの最適化
オンプレミスからのリフト&シフトで、旧世代の gp2 ボリュームをそのまま使い続けているというケースは多いようです。
そのため、AWS へ移行してもコストメリットにつながらないといった課題があります。
これらは、必要に応じて新世代のボリュームタイプへ移行することでコスト最適化を図ります。
- 「gp2」から「gp3」へ
- 「io1」から「io2」へ
また、それぞれの新世代ボリュームは、コスト・パフォーマンスともに優れているそうです。
管理とモニタリングツール
EBS のコスト最適化についても、いくつか管理、モニタリングに利用できるサービスがあります。
- Elastic Volumes
- アプリケーションのニーズに合わせて、柔軟にボリュームの調整ができます。
- またこれらは、完全シームレスに実行され、ダウンタイムやパフォーマンスへの影響が出ません。
- Cost Optimization Hub
- 組織全体で、AWS のコスト最適化のレコメンデーションを特定してくれます。
- EBS について検索することで、削除、アップグレード、リサイズなどをレコメンドしてくれます。
- AWS Trusted Advisor によるコスト最適化
- コスト最適化のベストプラクティスとして不要な EBS や、スナップショットの特定ができます。
3. パフォーマンスがコストに及ぼす影響
このセクションでは、ストレージのパフォーマンス向上が実際にコスト削減にどのように寄与するかについて説明されていました。
ストレージでボトルネックが発生してしまう場合、結果的にコンピューティングにかかるコストが増加してしまいます。
そのため、ストレージのパフォーマンスを向上させることで、これらの高価なコンピュートリソースの稼働時間を短縮し、結果的に大幅なコスト削減を実現できるということでした。
まとめ
本記事では、「クラウドストレージのコスト最適化戦略 – AWS ストレージの賢い活用法」というセッションについてご紹介させていただきました。
ストレージのコストに焦点を当てて最適化するためにできることがまとまったとても良いセッションだったと感じました!
本ブログでは紹介しきれない内容もございますので、気になった方はぜひアーカイブでチェックしてみてください!
少しでも参考になれば幸いです!
最後までお読み頂きありがとうございました!
テックブログ新着情報のほか、AWSやGoogle Cloudに関するお役立ち情報を配信中!
Follow @twitter2024年新卒入社。うどん好きな初心者クラウドエンジニア。
Recommends
こちらもおすすめ
Special Topics
注目記事はこちら

データ分析入門
これから始めるBigQuery基礎知識
2024.02.28

AWSの料金が 10 %割引になる!
『AWSの請求代行リセールサービス』
2024.07.16




