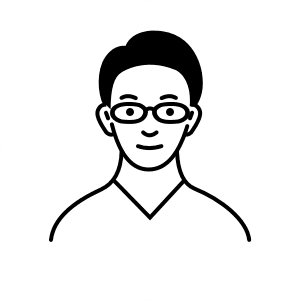SENSORS IGNITION 2017 REPORTS

UITのmoriです。投稿が少し遅くなってしまいましたが、3月23日に虎ノ門ヒルズフォーラムで行われたSENSORS IGNITION 2017に行ってきたので、その内容をレポートします。
SENSORSというテクノロジー ✖ エンターテイメントの情報番組があるのですが、その番組主催のイベントです。SENSORS企画チームが日本の気になっているアーティストや研究者に取材、フォーカスし、その舞台裏を掘り下げ、番組を通じて発信し、日本を盛り上げていこうといった意図を感じました。
以下のタイトルそれぞれに45分ずつの対談でした。(一部15分)
- 『グローバルに通用するクリエイティブとは?』MIKIKO, 真鍋大度
- 『VRクリエイティブ最前線』齋藤精一, 秋山賢成, 土屋敏男
- 『AI×映像認識の最前線』米田大介, 花ヶ崎伸祐(15分)
- 『近未来社会予測 ~AI、ロボット~』神山健治, 落合陽一
- 『メディアの先駆者が語る!これから生き残るコンテンツとは?』古田大輔, 佐藤ビンゴ, 栗原甚
- 『テレビ×ネットで生み出すTVCMの新しい価値』吉澤健吾(15分)
- 『日本3.0 日本の将来、何に投資すべきか?』高宮慎一, 佐藤真希子, 斎藤祐馬
- MIKIKO(演出振付家)
- 真鍋大度(メディアアーティスト)
登壇者は、Perfumeの舞台演出で有名な真鍋大度さんとダンサーのMIKIKOさんです。ドイツから帰国したばかりで、そこで行われたCeBIT 2017というイベントでのオープニングセレモニーの内容が中心となり対談が進みました。
グローバルにどう通用させるのか、その答えの一つに真鍋さん率いるプロジェクトメンバーの「高い専門性」とその「コラボレーション」がキーになっているんだなと感じました。未踏領域の技術を真鍋さんが提案し、それをもとにダンサーさんが実際のパフォーマンスの構想を練る、筋肉の動きに理解のある森山未來とコラボレートし、その化学反応をみる。初めからすべてを思い描いて作為的に作るのではなく、自分のできることのみ専念し、あとはそれぞれのメンバーに託す。そんな志の高さがグローバルに通用したのではないかと思います。
要点まとめ
- 過去の作品を徹底的にリサーチ。そこから今回の表現の流れを見出す
- 今回のパフォーマンスの原点は、バウハウスのパフォーマンス(参考動画)で、今回の作品はその発展形となる
- リオ五輪閉会式での話、本番環境でのリハは不可。3Dシミュレーターを自作し、イメトレした
- 本番ではライト等の機材の位置が想定よりずれることが予想されたため、調整機能を事前に実装した
- リオでは、ダンサーがカメラを持っており、会場にいる人は生のダンサーを、テレビを見ている人はそのダンサーのカメラ映像を見る
- 衣装にはLEDではなく、有機ELを使用、LEDよりやわらかな光がでる
- 筋肉の電気信号を取得し、音がでる。筋肉を動かす前から音がなり始めるのがダンサーとしては難しかった
- ARの中で、実際の物体がトランスフォームするような表現を考えた。そのために立体物にオリジナルのマーキング手法を考察した
- 実際のスタジアムを3Dスキャンして、シミュレーターを作成した
- いくつかの招待制なクローズドなメーリスに入っている。そこで技術情報や、きになるイベントの技術の解体を行っている
登壇者
- 齋藤精一(Creative Director / Technical Director : Rhizomatiks)
- 秋山賢成(ソニー・インタラクティブエンタテインメント・ジャパン・アジア)
- 土屋敏男(日本テレビ 日テレラボ シニアクリエイター)
続いての登壇は、ゴースト刑事という「並行進行のドラマ」をアプリでリリースした御三方のお話です。内容につきましては、上記動画をみていただくのが一番わかりやすいと思います。
面白かったポイントは、「それを見ているユーザーは何者なのか?」という観点です。自分が誰かわからないままその仮想世界に飛び込むと、誰かわからないけど存在するという意味で、「VR酔い」が起こると言っていました。そこで、このゴースト刑事では、ユーザーは幽霊の刑事となりその視点で見ることで、違和感なく没入できるようにしたそうです。
要点まとめ
- 番組のキーマンは、日テレの土屋さん(電波少年作った人)
- 10年前に、セカンドライフというサービスを通してすでにVR動画配信をリリースしたが世間がついていけず、今回は胸張ってリリースした
- 技術面のアドバイザーにはRhizomatiksの斎藤さん(冒頭の真鍋さんと同じ会社の人)とソニーの秋山さん(PSVRの製作者)
- 日テレチームにVRのノウハウはないので、2人にアドバイスもらいながらノウハウを蓄積していった
- まず始めにカメラを使い、何m離れて撮影するのか検討を始めた
- 4つのカメラで撮影し、それを1枚の絵につなげる作業を行った(スティッチ)
- 制作コンセプトは「没入感」無自覚にその世界にいる感覚
- 今までのドラマは「神の視点」、ゴースト刑事は「幽霊の刑事」
- 2017年はVRの技術面ではなく、何を作るのかというコンテンツの年になる(Sonyの秋山さん)
登壇者
- 米田大介(NEC 放送・メディア事業部 新事業推進部長)
- 花ヶ崎伸祐(NECソリューションイノベータ イノベーション戦略本部 戦略グループ 主任)
お次はNECさんです。とてもお固いイメージをみなさんお持ちかもしれませんが、実は精度の高い画像解析を通して、様々な取り組みをやっています。
登壇の話の中で面白かったのが、フィッシュカウンターです。魚の市場で、パイプの中を魚が通っていくのですが、それを画像認識を使って、魚の数をかぞえるアプリを作ったそうです。他にもマラソンのゼッケンナンバーを自動で読み取るソフトなど、非常にニッチな分野にも手を出しています。
要点まとめ
- NECの画像認識技術は人、顔、属性(23歳、男性、笑顔)、分類、動物、カウント、追跡、物体検出、OCR
- 最近だとトキワ荘でのスタンプラリーアプリをリリース
- 笑顔でバトル!吉本工業とコラボし、実際にお客さんにウケているのか数値で算出
- 顔からその人に合うファッションを提案するアプリ
- Neofaceという世界No.1の画像認識精度を誇っている。以前にもARはやっていたが、少し先取りしすぎた
- NECとのコラボの機会は少ない、SENSORSのような機会を通して、みなさんからのコラボレートの連絡待っている
- IoTという言葉がはやる前からIoTを実践してきた
- only1の技術力と高い組織力で競合と戦っていく
登壇者
- 神山健治(アニメーション映画監督)
- 落合陽一(メディアアーティスト,筑波大学助教デジタルネイチャー研究室主宰,VRC理事)
続いては、攻殻機動隊や東のエデンなどのヒットアニメを生み出した神山健治さんと筑波大学助教授の落合陽一さんの対談です。公開されたばかりの映画「ひるね姫」と日本人の世代に関してお二人が熱く語ってくれました。
この対談で面白かったポイントは現在の日本の混沌を映し出すというところです。日本の成功事例である自動車やオリンピックを体験してたおじいちゃんの世代、そしてそれを見つつ打破しようとする世代、それらを全く知りもしない世代、その3つの化学反応をみたかったと監督がおっしゃってました。通常は1つの映画に1つのテーマですが、この映画では2.5個ぐらいのテーマを盛り込んでいるそうです。
要点まとめ
- その時々の社会テーマとして大きな題材となるものをとりあげ、それを映画に落とし込んで社会の反応を見る
- 今回のテーマは「自動運転」。そして、主人公としては、個人として生きている社会にあまりコミットしていない人が、最終的にコミットするという、今までとは逆のアプローチをとった
- 3.11の事件をずっと意識しており、あの事件がきっかけに何も起きない日常がファンタジーとなった
- 現実に起きていることに目をつぶれば平和でハッピー。なので、主人公は社会にコミットしていない人物像を設定した
- 昨今の映画の変化として、映画自体がインタラクティブになっている
- 映画が公開されるとTwitterやFacebookで何かしら反応がある、監督自身もその反応をもとに、次の映画を作ったりする、つまり視聴者自身も映画作りの一人となる
登壇者
- 古田大輔(BuzzFeed Japan創刊編集長)
- 佐藤ビンゴ(Vice Media Japan inc. CEO, Genral Manager)
- 栗原甚(日本テレビ 演出・プロデューサー)
- BuzzFeed
- VICE Japan ※現在リンクは削除されています(https://www.vice.com/jp/)
- Dragons Den (イギリスのマネーの虎)
これまでの登壇では制作者という観点の人たちが多かったですが、お次はメディアを操る3人の対談です。1人目はシェアしたくなる記事を送り出しているBuzzFeedの古田大輔さん、そして過激な内容で興味をそそるVICE Media Japanの佐藤ビンゴさん、そして、マネーの虎の生みの親、日本テレビの栗原甚さんです。お三方とも非常に内容が濃く、勉強になりました。
特に面白かったのは、「マネーの虎」が形を変えて世界中で放送されているということでした。日本での番組終了後、その番組フォーマットを世界中の番組会社に販売しているとのことです。中国での話が面白く、日本の農作物を販売する提案をしたところ、一人4億づつ出資し、合計20億がその番組内で集まったそう、さすが中国といった感じです。
要点まとめ BuzzFeed
- 「いかにシェアされるか」だけをただひたすら考えてここまでサイトを育てた。最近SEO対策意識しはじめている
- なぜFaceBookに自分の写真をあげるんだろう?自分をもっとよく見せたいだとか、ユーザーの心理を探る
- 「バズる」の定義は「読んでもらったものがシェアしてもらう、コメント、エンゲージしてもらう」
- 知識、感情、アイデンティティ,アスピレーション(これやってみたい)といったことに人の心が動く
- 人の心を動かすものはどの国の人も変わらない。ただ、「何」に対して心が動くかは国ごとにことなる
- エンターテイメントからシリアスな話、料理ネタまで、様々な分野の記事を書いているが、国ごとに合わせてその内容は変えている
要点まとめ VICE Media
- 発端としては、インターネットというのは不確かな情報が一瞬で広がる、ではその検証をやってみましょうということ
- VICE Mediaは悪がメイン、そして正義も少し。話題としてはイスラム人、麻薬カルテルとか…
- あえてコンテンツに対して意見を言わず、ただありのままにその映像を見せている
- ずっと現地の人に密着すると、暮らしや目つきが変わってくる、そんな内容までも記事をみることで感じることができる
- 一般の人がもつ疑問をちゃんとぶつけている、逆にプロにはできない、だからこのサイトにしかない情報がある
要点まとめ 日本テレビ 栗原さん
- カンヌでフォーマットを売り込むためのプレゼン動画を見せたら、はじめにソニーピクチャーズが購入、一気に世界に広がった
- 現在では、31カ国で、各国の制作のもと放送されている
- それぞれの現地に足を運び、しっかり番組が制作されているか、アドバイスし監修している
- 今もずっと各国で放送が続いているが、その秘訣は「アフターフォロー」
- イギリス、カナダ、ドイツ、などの番組プロデューサー同士で集まり、会議を開いた。これをやるとまた、継続する
登壇者
- 吉澤健吾(HAROiD inc. Business Development Manager)
登壇者はHAROiDという会社の方で、内容は最近テレビCMとスマホアプリを連携してインタラティブなCMを作った話でした。視聴者がアプリ上で合計600万タップすると15万円分のクーポンコードを発行し、それをユーザーがもらえるというインタラクティブなCMです。
印象に残ったのは「国民総出のお祭りに参加したような感覚」を提供するという話です。実際にユーザーがもらえる金額は150円ですが、リアルタイムでCMを見ている人と一緒になってタップし、実際にコンビニに行ってビールをもらう、中には久しぶりにコンビニでビールを買った人もいたそうです。そんな体験には150円以上の価値があるとおっしゃっていました。
要点まとめ
- CMが流れている最中にアプリを起動しないといけない
- 事前に告知してたが、当日のCMでそのキャンペーンを初めて知った人がほとんど
- 60秒の尺のうち、30秒を説明に、そして30秒でユーザーにアプリからコミット
- CMコンテンツ制作の受注フローがまだ整っていないので、コラボに興味がある人はまずは相談してください
登壇者
- 高宮慎一(パートナー/Chief Strategy Officer グロービス・キャピタル・パートナーズ)
- 佐藤真希子(株式会社iSGSインベストメントワークス取締役代表パートナー)
- 斎藤祐馬(トーマツベンチャーサポート株式会社 事業統括本部長 公認会計士)
トリを飾るのは投資家のお三方です。普段僕と接点のない投資家の方の話だったのでまぁ難しかったです。
対談の中で、なんども話にでたキーワードが「ニッチ」でした。今やGoogleやFacebookなどの大衆向け大手のサービスにばかり目がいきがちですが、その反面、SHOWROOM(DeNAの子会社)や地下アイドルのような市場が生まれており、そのユーザー層というのは、アープ(ユーザー1人あたりの売上高)が高くエンゲージ率も高い、そこに投資するのはハイリスクハイリターンだが、チャンスがあるとのことです。
要点まとめ
- 「2020年」頃から日本に変化が起こる。ビジネス界で、大企業とスタートアップの境目がどんどん薄くなっていく
- 現代のサービスというのは、ガラケーやPCでできていたものをスマホに最適化しただけ。じゃあ今できていないのは?というと、それは濃いファンに向けたサービス
- SnapChatなんかはその一つの例。Facebook疲れから生まれたサービス
- グローバルなソーシャル文化が栄える一方、小コミュにが生まれる。Instagramなんかはその現れで、トップアイドルが行っていることを身近な人がやる
- AI、再生技術、など次世代の技術は、「過剰期待期」そして次に「がっかり期」、最後に「やっとビジネスにおちつく期」となる
- AIはいまがっかりフェイズ、むしろ抜け出そうとしている
- ベンチャーは、ビジネスとしてソリューションとして拡散できるか、スタンダードとして舵をきれるかが重要
- ベンチャーが生き抜くには、江戸時代からもっているような市民文化(非グローバル)が大事
- 会社の方向性を要素技術で絞り込むのではなく、分野で絞る
- 大手のエンジンを使い、それをどう最適化するかがポイント
- 日本の厳しい環境の中で育ったものを海外に輸出するのも手
- インターネット領域だけでできることが飽和すると、それ以外の領域はハイリスクハイリターン
- 登るべき山を示して周りを巻き込んでいけるか(ビジョンとパッション)、新しいことをやると疲れるが、それをやり続けられるか(パッション)、それができる人材が求められる
- 独立した起業家は100人にプレゼンする。大企業内では、4、5人のみプレゼンする。マインドが全然違う
- 大企業内でチャレンジした時のリスクっていうのは、いじめられたり、給料上がらなかったり、ただそれだけ。いったん成功すると、みんな応援する
- 大事なのはプレゼン力(共感力)、そして次にロジック(震えさす)、最後に政治が大事。
- 今新しい分野で成功した人が2020年に役員になっていく、非常にチャンスな時
今回イベントで登壇された方々は、持ち時間45分では足りないとみんな言っていました。みなさん情熱がすごいです。みんな自分のやりたいことを仕事にし、それを楽しんでいるからこそ、他の人とのコミュニケーションが楽しいのだなと感じました。
長い記事となってしまいましたが、それだけ内容が濃かったです。読んでいただきありがとうございます。
テックブログ新着情報のほか、AWSやGoogle Cloudに関するお役立ち情報を配信中!
Follow @twitter2016年にフロントエンドエンジニアとしてUIT室に中途入社。それまで6年ほどGUIデザインをやっておりました。移り変わりの激しいフロントエンド業界で奮闘しながら楽しく仕事をしています。
Recommends
こちらもおすすめ
-

コンテンツ東京2017でVRしてきた☆
2017.7.6
-

手を動かして GBDT を理解してみる
2019.5.24
-

データサイエンス関連参加イベントまとめ(2017年)【前半】
2017.12.1
Special Topics
注目記事はこちら

データ分析入門
これから始めるBigQuery基礎知識
2024.02.28

AWSの料金が 10 %割引になる!
『AWSの請求代行リセールサービス』
2024.07.16